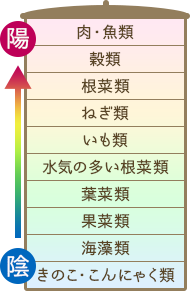ごはんの雑学
2018.09.07
かんぴょうの原料は夕顔で夏に収穫され、実を細長い帯状に剥いて加工されたものです。効能は余分な熱を冷まして水分代謝を促進し、ほてりや渇きを抑えるなど暑い夏にはうれしい食材ですが、あまり使われませんが食物繊維も豊富です。胡瓜と合わせることで水分やビタミンCがとれ美肌効果も期待できます。

エネルギー(1人分):25kcal
塩分(1人分):0.7g
| 材料と作り方(6人分) |
◆作り方 |
2018.04.10
アヒージョとはスペイン料理で小さなにんにくをオリーブオイルで煮込む小皿料理のこと砂肝は消化器系のはたらきをよくして消化を助け、春に関連する肝の機能を整えます。
生薬に鶏内金(砂肝の乾燥品)があり胃腸の不調時に処方されます。今回はオリーブオイルで煮込むことで軟らかくコリコリ感があり、香りもよく食べやすいです。おしゃれな1品が手軽にできます。

エネルギー(1人分):133kcal
塩分(1人分):0.8g
| 材料と作り方(6人分) |
◆作り方 |
2017.10.09
秋の邪気は燥邪。肌も髪もパサついてませんか。この時期は断然白きくらげをお勧めします。潤肺作用といい肺は皮膚と密接に関係しているため、美肌効果に白きくらげが良いといわれています。
一般的になじみの深い黒きくらげは血を補う効果が高いので血を増やして血をめぐらせる効能があります。
今日のサラダは白・黒のきくらげを使い美肌にも貧血にも効きます。
大型スーパーで手に入りますが国産は希少価値です。先日、国産の白きくらげ見つけましたので参考にしてください。
http://www.asukakikurage.co.jp/shirokikurage.html

エネルギー:50kcal
塩分:0.6g
| 材料と作り方 |
◆作り方 |
2017.06.19
おからがベースのでヘルシーなサラダです。具は重ね煮、木耳・玉葱・コーン・人参で彩りよく、で女性に多い便秘対策にも効果。
その上おからを炒って牛乳でなめらかに仕上げるにで、とても食べやすいです。ここに胡瓜などを加えるとポテトサラダのような仕上がりです。

エネルギー:108kcal
塩分:0.6g
| 材料と作り方 |
◆作り方 |
2016.11.13
秋は燥邪により喉・肺・皮膚・髪の乾燥が気になる季節です。白い食材を使うことで体内を潤す効果があります。
長芋、卵白、上新粉などの白い食材を使った和菓子です。小麦アレルギー方にも安心!

エネルギー(1個): 90kcal
| 材料と作り方(10個) |
◆作り方 |
2016.07.12
女性に多い血のトラブル、ひじき・人参で補血効果(造血機能の促進)、玉ねぎで活血(血の巡りの改善)が期待できます。梅干しを加えること夏バテ予防も期待できる1品です。

エネルギー: 68kcal
重ね煮
塩分: 1.2g
| 材料と作り方(1人分) |
◆作り方 |
2016.03.14
| 材料 |
|

1. 前日に準備すること
★大豆は洗って約3倍の水につけておく
★麹と塩はまんべんなく混ぜ合わせておく(塩切り麹)

2. 大豆を火にかけ沸騰させないように火加減に注意して指でつぶせるようになるまで煮る(3時間ぐらい)

3. 大豆はざるに上げてすりこ木またはマッシャーで潰す

4. ゆで汁は30分ぐらい煮詰めてとろみをつける(飴という)
5. つぶした大豆と前日に準備した塩切り麹をまんべんなく合わせ4.の飴で柔らかさを調節する

6. 焼酎などで殺菌した容器にボール状に丸めた味噌玉を容器に空気が入らないように投げ入れていく

7. 最後は平らにしてラップをして塩枕(晒しを袋状に縫い約1キロの塩を入れたもの)をのせ、蓋をして8ヶ月ほど置く
(3ヶ月ぐらいに表面に水分が出ていたら底から全体を混ぜ合わせ天地返しをする)
2015.12.12
冬は腎(じん)」が消耗しやすい季節です。腎の働きは、体内の水分代謝のコントロールのほか、ホルモン、生殖器、泌尿器、免疫系などを司るシステムのことで、「生命力の貯蔵庫」ともいわれ、冷えを嫌います。生ものや冷たい飲み物などは避け、胃腸を酷使する年末年始は消化の良い食材を使った温かいスープで体の芯から温まってください。

| 材料と作り方 |
◆作り方 |
2015.09.15
秋は空気が乾燥し、人間の内蔵・肌・髪なども乾きやすくなります。鼻の乾き、咽喉の痛み、咳、胸の痛みといった呼吸器系の病気が発生し易くなります。秋を元気に過ごすには肺の働きを助ける白い食材が体を潤してくれます。
白い長芋と粘りとカロテンが豊富なつるむらさきで元気が出る1品をご紹介します。

| 材料と作り方(6人分) |
◆作り方 |
2015.06.20
1年のちょうど折り返しになる6月30日に京都では半年の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願する神事が行われます。この時期、夏痩せせずに元気で過ごせるようにという意味を込めて和菓子「水無月」を食べる習慣があります。
氷室の氷で暑気払いをしたため氷の形を表した三角形で上にのせる小豆は悪魔祓いの意味があるということです。
昔の人は季節に合わせて食べ物に様々な思い込めて暮らし、飽食の現代よりもとても豊かな食生活を送っていたようですね。

| 材料と作り方(20×7センチの耐熱容器) |
◆作り方 |
2015.03.20
五行説では春の五味は「酸味」です。「酸味」には気や血を巡らせて筋肉を緩める作用がありますが摂りすぎると筋肉をこわばらせたりします。自然の甘みと一緒に摂ることが体調管理には必要です。
そんな季節にぴったりのサラダです。
クコの実を柑橘系の絞り汁1:米酢1の割合に漬け込んだものを使い、自然の甘みが楽しめます。

| 八朔サラダ(6人分) |
◆材料
|
◆作り方
① ボールに★の調味料を合わせる
② 八朔・胡瓜・生わかめを混ぜる
③ 器に盛り付ける

材料は3つ

クコの実も一緒漬け込み冷蔵庫で保存(1ヶ月保存可能)

他の柑橘類でも美味しい
2014.12.14
A) 悪寒で体のぞくぞく冷える感じが強い場合・・・風寒感冒
辛温解表(温めて体表に現れる症状を除く) 紫蘇・生姜・ネギ・シナモン・黒砂糖
B) 寒気は少なく初期から頭や体が熱っぽい場合・・・風熱感冒
辛涼解表(熱をとり体表に現れる症状を除く) 菊花・ミント・緑茶
C) 急な嘔吐、下痢、腹痛など胃腸炎の症状でウィルスが原因の夏風邪・・・風湿感冒
D) インフルエンザウイルスの感染で経路は空気感染または飛沫感染などで発症・・・流行性感冒
1.~4.とも予防のためには手洗い・うがいを励行 特に緑茶でうがいをするとカテキンで殺菌効果が高い
★梅醤番茶
番茶の中に種を取った梅干しを入れて、スプーンでつぶして飲みます。
梅干しは疲労回復に役立つクエン酸や、抗菌や滅菌作用のあるカテキンなどが含まれています。 この梅干し茶に醤油(吸い物より薄め)とショウガのおろし汁を加えると、パワーがアップした「梅醤番茶」が出来上がります。食前か空腹時に飲むとよいとされています。
★甘酒
飲む点滴と言われるぐらい、甘酒にはすごいパワーがあります。
特に米麹を糖化(とうか→デンプン質を糖分に変化すること)させて作ったものには糖質、脂質、蛋白質の代謝に必要なビタミンB群が豊富。それに体に必要なアミノ酸も多く疲労回復、体力増強にも効果があります。
コウジ酸、オリゴ糖による美肌効果と便秘の改善と良いことだらけ。
今回は鍋帽子で簡単甘酒(いんやん倶楽部 http://yinyanclub.com/about/ のレシピ参考)作ってみました。

① 七分づき米1カップを洗い30分ほど浸水させてから5カップの水でお粥をたく
土鍋を使うと20分で美味しいお粥が出来上がり

② その中に米麹300gと湯冷まし4カップを加え62℃に調節

③ 蓋をして鍋帽子(保温調理のための鍋専用の帽子) をかぶせ6時間放置

④ 6時間経て糖化された自然の甘みの甘酒の出来上がり。冷蔵庫で保管すれば1週間はOK

⑤ そのままでも美味しいですが、フードプロセッサーで潰し土生姜、黒砂糖をかけたりヨーグルトと合わせたりいろんな楽しみ方ができます。
2014.12.14
冬は気温が低下して寒さの影響を受けやすくなり、毛細血管が収縮して血の巡りが悪くなります。対策としては充分な睡眠をとり寒さ対策が必要となります。首筋、手首、足首などから寒邪の入るのを防ぎ温暖に過ごすように心がけましょう。
体を温める食材と「気」「血」の流れをよくすること大切です。
気を補い体力を増強させるには
「補気」・・・・玄米・やまいも・なつめ・椎茸・人参・いか・鶏肉
栄養を与え造血機能を促進させるには
「補血」・・・・黒豆・ごま・松の実・クコ・黒きくらげ・ほうれん草・あさり・かき・うなぎ・鮭・牛乳、豚肉
循環促進させ腎系へ働きかけるには
「補陽」・・・・ニラ・ねぎ・栗・くるみ・ニラ・えび・シナモン・羊肉
2014.09.30
薬膳調理の基本に「一物全体」という考え方があります。
選び出した食物はそれ自身が備えている効能を存分に引き出さなければならないという考えかたです。食材を丸ごと使うことで、皮をむかない・根菜なら葉もいただく・小魚なら骨ごといただくことで食物の生命をありがたくいただくことという意味です。私の日常生活においてとても共感できる考え方です。
さつまいもの収穫時期が近づいてきました。
サツマイモの苗ってとても生命力が強く、伸びたつるからも発根して根付きます。そうすると伸びたつるに養分が取られてしまうので、「つる返し」という作業を行い美味しいさつまいもができるようにします。
つる返しと言うのは、伸びすぎたつるを元のうねの方に、バサッとひっくり返すこと。 それを利用した佃煮をご紹介します。さつまいもよりつるの佃煮が楽しみという方もいらっしゃいます。

| さつまいもの茎の佃煮 |
◆材料
|

4センチ長さに切り熱湯でサッと茹でておく
◆作り方
①茎は熱湯でサッと茹で、3センチ長さに切る

鍋でごま油で炒め調味料を加え煮含める
②鍋にごま油を熱し茎・ちりめんじゃこ・山椒の実を加え全体をなじませる
③調味料を加え混ぜながら煮汁がなくなるまでいりつける。
2014.09.30
秋は収穫の季節で気候は涼しくなり肺の故障が起こりやすくなります。
空気の乾燥により「燥邪(そうじゃ)」による不調が出てきます。
多い症状は肌の乾燥、のどの痛み、空咳、鼻の乾燥などで「清熱・潤燥」「滋陰・潤肺」作用のある食物を取り入れましょう。
乾燥症状を潤すには潤燥
⇒大豆、豆乳、豆腐、梨、牛乳、牛乳などの白い食材
陰を補い清熱・潤い効果は滋陰
⇒黒米、豚肉、鶏卵、アワビ、牡蠣、あさり
肺経のトラブルを解消する潤肺
⇒りんご、梅干、白木耳、柿、羅漢果などの酸味のある食材

「秋の潤いデザート:杏仁豆腐」
●杏仁(あんずの種)・・・・肺に作用し咳や痰を取り除く。脂質を含み腸を潤し便通促進効果もある
●牛乳・・・・・・・・虚弱をたすけ、肌や腸を潤すので、肌の乾燥や便秘にもいい。
2014.08.18
土用干し開始・土用干しとは夏の土用の晴天の日に梅の塩漬けを日干しにすること

1日目(7/25) 快晴 夜も室外で夜露にあてる

2日目(7/26) 快晴

3日目(7/27) 午後曇り 午後から曇り空のため室内へ

4日目(7/28) 快晴

5日目(7/29) 土用干し完了
| 一口メモ |
| 干すことで紫外線の効果で表面などの微生物を殺菌。プラス梅の水分をとり保存性と殺菌効果を増幅させる。 昔副産物の梅酢は漢方としても利用されていた。 梅のクエン酸が疲労回復や防腐効果があるため昔から日の丸弁当として馴染みが深い。 |

梅酢・ざらめ入り

梅酢・ザラメなし
梅を干すことで梅の色とシワの変化がよく分かり、室内に取り入れた時のふくよかな良い香りは梅仕事を味わって初めて体験。今回は梅酢に戻しザラメをパラパラとふったものと、土用干し完了の梅を保存便に入れそのまま保存したものと2種類作りました。手作りの楽しさと梅の偉大な力を再確認!
来年も挑戦しようと思ってます。
2014.08.18
料理の味加減に塩梅(あんばい)と言う言葉を使いますが、塩と梅酢の下限がちょうどよい状態の時に使われます。ちょうどこの時期梅を漬ける頃ですが、結婚して初めて梅干をつけてみました。
今まで漬けなかった理由は、母がなくなった年に実家の梅干が初めてカビが発生しそれに気づいた母が良くないことが起こると悲しんでいた悲しい記憶があるからです。
ことわざに「梅干しが腐ると不幸が起きる」という言葉を信じていたからだと思いますが、実際その年の梅干がカビてしまったのです。ところが若き薬膳仲間が毎年梅干を漬けていることを知り今年は我が家の梅も大粒だったのでチャレンジしてみました。今までの工程です。

《材料》
青梅 2.4 kg
塩 360g(梅の 15%)
焼酎 適宜
赤紫蘇 240g
塩 大さじ 3
《つくり方》

① 青梅はきれいに洗ってヘタを爪楊枝などで取る
(梅のエキスが出やすいようにするため)
② きれいに水気を取ってから梅を少しずつ焼酎を絡ませる(カビ予防)

③ 分量の塩のうち大さじ 1~2 程度をまぶす

④ 容器に塩をふり(敷塩)③の梅⇒塩⇒梅⇒塩を繰り返す

⑤ 重石をして梅酢が上がるまで置く

⑥ 5日後
赤紫蘇をきれいに洗い、大さじ1杯強の塩をまぶし揉み汁を捨てアク抜きをする

同じく塩をまぶし揉み固く絞り⑤の梅酢を 100cc 程度加えほぐした紫蘇を梅の上の載せ再び重石をする

⑦ 3日後の様子
食べ物の力ってすごい!赤紫蘇のアントシアンでこんな色に・・・
梅雨が明けるまで1日 1 回は点検していよいよ梅干しのクライマックス土用干へ・・・・失敗しませんように
次回ご報告までしばらくお待ちください
2014.05.19



土用の丑の日とは 立春、立夏、立秋、立冬までの18日間のことです。1年で本当は4回あるわけですが何故か夏バテとセットで夏のうなぎだけが有名になっています。
夏に食べる理由はタンパク質や良質の脂質が多く、体力回復やビタミンA・B・Eが多く目や老化防止に加え新陳代謝を活発にします。
薬膳的にも補気、補血、活血、祛風湿などの効果があり夏のうなぎは理にかなっていると言えます。
今年は7月29日(火)になりますが最近うなぎの値段が高騰してなかなか手が出ません。
そんな時には「う」のつくものを丑の日に食べると災難から逃れると言われています・・・・・下記をご参考に
うどん・・・・・のど越しがよく食欲のない時にも食べやすく消化も良い。
梅干・・・・・酸味が食欲増進し、含まれるクエン酸に代謝促進効果がある
瓜類 ・・・・・体内の余分な熱を冷ます効果があります。利尿効果もあるので、むくみ防止にもなります
2014.05.19

夏は気温が上がり生長が加速して心気が強まる季節です。
心経のトラブルを防ぐためには清熱(体内の熱を取る)
⇒トマト、ハトムギ、緑豆、豆腐、金針菜、冬瓜、ニガウリ、すいか、胡瓜、メロン
暑熱に対応できるよう解暑(暑さを取り除く)
⇒すいか、パパイヤ、まくわ瓜、緑豆、粳米
汗のかき過ぎには生津(体内の津液※補給)
⇒豆腐、トマト、白キクラゲ、梨、桃、レモン、ライチ、牛乳
津液※とは・・・・身体の一切の水分の総称
 ① 冷たいものを摂りすぎると胃脾を弱め、消化機能が低下しやすいので要注意。
① 冷たいものを摂りすぎると胃脾を弱め、消化機能が低下しやすいので要注意。
② 睡眠不足などにも気をつけてイライラや不眠対策になる小麦、蓮の実、わらび、桃、ナツメ、百合根なども取り入れる。
2014.02.06
「春は苦みをとれ」という言葉を聞いたことがありますか?
これは陰の冬の時期に体に溜まった老廃物を苦味のある野菜をとることで
陽の春を迎えるにあたり体内をリフレッシュさせる効果があります。
雪の下から一番先に芽を出す「蕗のとう(ふきのとう)」があります。
苦味成分のアルカノイドは肝機能を強化し、新陳代謝を促進します。
薬膳の効能としては健胃・解毒・止咳・通便の効能。
| 蕗のとう味噌汁 |
|
≪材料≫ 蕗のとう ごま油 白味油 赤味噌 酒・みりん ≪作り方≫ ①蕗のとうを細かく刻み厚手鍋にごま油を熱し細かく 刻んだ蕗のとうを炒める。 ②しんなりすれば味噌、みりん・酒などで好みの味にする。 |
苦味のある春野菜は菜の花、のびる、こごみ、うど、などが楽しめます。
![菜彩クッキング [薬膳家庭料理教室]](img/head_logo.gif)